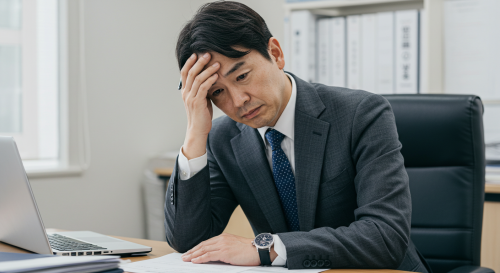ブログ
まずはここから!健康経営を始めるための第一歩【お問い合わせ事例より】
「最近、社員の生産性が落ちている気がする...」
「働き方改革を進めているのに、なぜか若手の離職が後を絶たない...」
「社員の健康診断の結果を見て、何か対策を打たなければと焦りを感じている...」
企業の未来を真剣に考える経営者様、そして人事・総務担当者の皆様。
このような、一つひとつは小さな棘のように感じられる経営課題が、
実は組織の根幹を揺るがす深刻な問題に繋がっているとしたら、どう思われますか?
現代の日本企業は、少子高齢化・労働力人口の減少という、
避けることのできない構造的な課題に直面しています。
限られた人材で、これまで以上の成果を出し、
企業が持続的に成長していくためには、もはや旧来の経営手法だけでは通用しません。
その突破口として、今、多くの先進的な企業が注目し、実践しているのが「健康経営」です。
しかし、「健康経営」という言葉は知っていても、「具体的に何から始めればいいのか、さっぱりわからない」というのが、多くの担当者様の本音ではないでしょうか。
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
本記事では、そんな皆様のために、私たちが日々いただく実際のお問い合わせ事例を基に、
健康経営を成功に導くための確実な第一歩を徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が、未来への具体的な行動計画へと変わっているはずです!
多くの経営者が抱える5つのリアルな悩み
私たちヒューマンフィットネス東浦が日々、
経営者様や担当者様からご相談いただく内容は、驚くほど共通しています。
それは、多くの企業が同じ根深い課題に直面していることです。
まずは、貴社の状況と照らし合わせながら、そのリアルな悩みをご確認ください。
事例1:「福利厚生はあるけど...」形骸化する制度への焦り
「社員のためにと思って、一般的な福利厚生サービスは導入しています。
ですが、正直なところ『利用率が低くてもったいない』というのが本音です。
巷で話題の『福利厚生ランキング』も参考にしているのですが、なぜか社員には響いていないようで...」
これは、非常によくあるお悩みです。
そもそも福利厚生とは、従業員とその家族の幸福と生活の質を向上させるための施策ですが、
他社の模倣や世間体で制度を導入してしまうと、自社の従業員の真のニーズとズレが生じます。
例えば、ある製造業の企業では、高額なフィットネスクラブとの法人契約を結んでいましたが、
実際の利用率は5%未満でした。
調査してみると、従業員の多くは
「仕事帰りにジムに通う時間がない」「家から遠い」という理由で利用を諦めていたのです。
結果として、誰も使わない「幽霊制度」となり、コストだけがかさんでしまうのです。
このような状況では、従業員の満足度向上はもちろん、企業としての投資効果も期待できません。
事例2:「オフィスが静かすぎる...」目に見えない生産性の低下
「特にリモートワークが普及してから、社員の『腰痛や肩こり・疲労』を訴える声が増えました。
オフィス全体に活気がなく、集中力が続かないのか、以前よりミスが増えた気もします。
『生産性が下がっているのではないか』と、経営陣も懸念しています」
これは、出社はしているものの心身の不調により本来の能力を発揮できない「プレゼンティーイズム」と呼ばれる深刻な問題です。
プレゼンティーイズムとは、「presence(存在)」と「absenteeism(欠勤)」を組み合わせた造語で、
職場にはいるものの、健康上の問題により十分なパフォーマンスを発揮できない状態を指します。
実際に、経済産業省の調査によると、
プレゼンティーイズムによる生産性損失は、欠勤による損失の約3倍にも上ることが明らかになっています。
従業員一人ひとりの小さな不調が、組織全体のパフォーマンスを静かに、しかし確実に蝕んでいきます。
ある企業では、午後の会議で居眠りする社員が増え、重要な意思決定に時間がかかるようになりました。
その背景には、長時間のデスクワークによる血流悪化と、運動不足による体力低下がありました。
事例3:「健診結果が怖い...」見て見ぬふりをしてきた健康リスク
「毎年の『健康診断の結果』を見るのが正直怖いです。
特に中堅社員を中心に、『メタボ社員、どうにか行動してくれないかな』と毎年思うのですが、
個人の問題として強く介入することもできず、有効な手を打てていません」
従業員の健康リスクを放置することは、
将来的に重大な疾病による長期離脱や、企業の医療費負担の増大に直結する、
経営上の「時限爆弾」を抱えているのと同じです。
個人の自己責任論だけでは、この爆弾を解除することはできません。
実際の事例として、ある中小企業では、40代の管理職が糖尿病で3ヶ月間の休職を余儀なくされました。
その間の代替人員の確保、業務の引き継ぎ、医療費の一部負担など、
直接的・間接的なコストは数百万円に上りました。
しかも、この管理職の健康診断では、
数年前から血糖値の異常が指摘されていたにも関わらず、適切な対応が取られていませんでした。
事例4:「また期待の若手が...」止まらない人材流出
「時間とコストをかけて育成した若手社員から、また退職の申し出がありました。
『また若手が辞めてしまった、なかなか人材が定着しないな...』と、もはや経営の最重要課題です。
待遇面だけでなく、働きがいや働きやすさといった面で、何か根本的な問題があるのかもしれません」
現代の働き手、特に優秀な人材は、
自身のウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に良好な状態)を非常に重視します。
ウェルビーイングとは、単に病気がない状態ではなく、心身ともに健康で、社会的にも良好な状態を指します。
従業員の健康に無頓着な企業文化は、エンゲージメントの低下を招き、
静かに人材流出を加速させるのです。
特に、長時間労働が常態化し、心身の健康を軽視する企業では、
優秀な若手ほど早期に転職を検討する傾向があります。
実際に、新卒で入社した優秀な営業職員が、入社2年目で退職した理由を聞くと
「会社に将来性を感じない」「自分の健康を犠牲にしてまで働く意味を見出せない」
という回答が返ってきたケースもあります。
事例5:「何から始めればいいか、わからない...」
「『健康経営』が重要だとは理解しています。
しかし、具体的に何から手をつければ良いのか、誰に相談すれば良いのか、全く分からず、結局何も始められていないのが現状です。」
この「わからない」という悩みこそが、最も多く、そして最も切実なご相談かもしれません。
情報は溢れているものの、自社に適した具体的な手法が見えないため、
結果として何も行動に移せないという状況に陥ってしまいます。
その悩み、解決の鍵は「健康経営」という新しい視点
前章で挙げた一見バラバラに見える悩みは、実はすべて「従業員の健康」という一つの根で繋がっています。
そして、その根っこから組織を元気に変えていく経営手法こそが「健康経営」なのです。
改めて、「健康経営とは」何か?
健康経営とは、一言で言えば、
「従業員等の健康管理を経営的な視点でとらえ、コストではなく『投資』として戦略的に取り組むこと」です。
これは、経営のOSをアップデートするような、根本的な発想の転換を意味します。
従来の考え方では、従業員の健康に関する支出は、
単に消えていく「経費」として捉えられがちでした。
しかし、健康経営では、その支出を、
将来的に生産性の向上、人材の定着、医療費の抑制、企業価値の向上
といった計り知れないリターンを生み出すための「戦略的投資」と位置づけます。
この「投資」という視点を持つことで初めて、
企業は場当たり的な施策から脱却し、経営課題の解決に直結する、
長期的かつ本質的な取り組みへと舵を切ることができるのです。
なぜ「健康経営」が時代の要請なのか?
この考え方は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。
労働人口減少社会の今、すべての企業にとって不可欠な経営戦略となっています。
厚生労働省の統計によると、日本の労働力人口は2008年をピークに減少を続けており、
2030年には現在より約200万人減少すると予測されています。
限られた人材で企業が成長していくためには、
一人一人が健康で元気に働くことがWell-beingな社会の実現に不可欠な時代なのです。
また、従業員の健康状態が企業の業績に与える影響も数値で明らかになってきています。
健康経営を実践する企業の株価は、
そうでない企業と比較して約5%高いパフォーマンスを示すという調査結果もあります。
従業員の健康という最も重要な資本を最大化することなくして、
企業の持続可能な社会における成長はあり得ません。
これは、単なる理想論ではなく、厳然とした経営の現実なのです。
健康経営がもたらす具体的な効果
健康経営を導入した企業では、以下のような効果が報告されています。
生産性の向上では、体調不良による作業効率の低下が改善され、
集中力の向上により品質の高い成果物の創出が可能になります。
従業員満足度の向上では、会社への信頼感が増し、モチベーションの向上につながります。
離職率の低下では、働きやすい環境の整備により、優秀な人材の定着率が向上します。
医療費の削減では、予防医学的なアプローチにより、将来の医療費負担を軽減できます。
企業イメージの向上では、CSR(企業の社会的責任)の一環として社会からの評価が高まり、
採用活動においても優位に働きます。
第一歩を踏み出すための3ステップ
「健康経営の重要性はわかった。でも、やはり何から始めれば...」。
ご安心ください。ここからが本記事の核心です。
誰でも、今日から踏み出せる「確実な第一歩」を、具体的な3つのステップでご紹介します。
STEP1:まずはお問い合わせを!「話す」ことで課題は具体的になる
驚かれるかもしれませんが、
健康経営の第一歩は、専門家に電話をかけ、悩みを「話してみる」ことです。
「こんな漠然とした相談でいいのだろうか...」と躊躇する必要は一切ありません。
私たちヒューマンフィットネス東浦の元には、日々そのようなご相談が寄せられています。
専門家である健康経営アドバイザーに話すことには、計り知れないメリットがあります。
まず、課題の言語化です。
頭の中でモヤモヤしていた悩みが、対話を通じて整理され、具体的な「課題」として言語化されます。
次に、客観的な視点の獲得です。
社内の人間だけでは気づけなかった、客観的な視点からの問題点の指摘や、新たな可能性の発見があります。
そして、安心感と信頼感です。
私たち、ヒューマンフィットネス東浦のトレーナー檜垣は、
健康経営アドバイザーであり健康経営トレーナーの資格を持つ専門家です。
貴社の悩みに寄り添い、本質的な健康経営を徹底伴走支援するという強い想いを持っています。
実際の事例として、ある製造業の企業様からは「漠然と社員の健康が心配だった」というご相談をいただきました。
お話を伺う中で、具体的には
「中高年社員の腰痛が多発している」「夜勤明けの事故リスクが高まっている」
という明確な課題が浮き彫りになり、効果的な対策を立てることができました。
STEP2:現状把握 - データに基づき「自社を正しく知る」
お問い合わせをいただき、ヒアリングを重ねた後の次のステップは、
思い込みや勘ではなく、客観的なデータに基づいて自社の現状を正確に把握することです。
身体機能チェックでは、専門のトレーナーが従業員一人ひとりの柔軟性、筋力、姿勢の歪みなどを測定します。
これにより、組織が抱える潜在的な身体リスクをデータで可視化します。
例えば、デスクワーク中心の職場では、首や肩の可動域制限、体幹筋力の低下などが数値として明確に現れます。
健康アンケートでは、生活習慣やストレスレベル、睡眠の質などを調査し、
組織全体の健康課題の傾向を明らかにします。
匿名性を保ちながら実施するため、
従業員も正直な回答をしやすく、隠れた課題の発見につながります。
このプロセスを経ることで、「なんとなく生産性が低い」という曖昧な問題が、
「営業部では、長時間のデスクワークによる体幹筋力の低下が課題である」といった、
具体的で論理的な打ち手に繋がる課題へと変わります。
これこそが、画一的な施策ではなく、
貴社だけのオーダーメイドプログラムを構築するための、揺るぎない土台となるのです。
実際に現状把握を実施した企業では、
「思っていた以上に深刻な問題があることがわかった」という声をよく聞きます。
同時に、「何をすべきかが明確になって安心した」という感想もいただきます。
STEP3:スモールスタート - 「これならできそう」から試してみる
いきなり大規模な年間契約や、大掛かりな制度改革は必要ありません。
現状把握で見えてきた課題に基づき、
まずは「これならすぐに始められそうだ」という施策から試してみることをお勧めします。
提案Aとして、意識改革の第一歩に「健康づくり研修(ヘルスリテラシーの向上)」があります。
まずは社員の健康意識の土台を作りたい、という企業様に最適です。
ヘルスリテラシーとは、健康に関する情報を適切に理解し、活用する能力のことです。
なぜ健康が大切なのか、自分の体を守るために何ができるのかを学び、
全社員の意識を同じ方向に向けるための、最も基本的なプログラムです。
提案Bとして、コミュニケーション活性化の起爆剤に
「出張フィットネス&セミナー」があります。
オフィスに活気がなく、社員同士の交流が減っていると感じる企業様におすすめです。
専門トレーナーがオフィスに伺い、皆で一緒に体を動かすことで、自然な笑顔と会話が生まれます。
組織の一体感を醸成する効果は絶大です。
提案Cとして、リモートワーク時代の新常識に「オンライン体操」があります。
在宅リモートワークが中心で、社員の運動不足が懸念される企業様には、
この「遠隔でもオンライン体操で元気に!」が最適です。
時間や場所を選ばず、「在宅勤務が多くても運動習慣化」を実現します。
提案Dとして、コストをかけずに始める情報収集に「YouTubeチャンネル」の活用があります。
まずはコストをかけずに、社内の健康意識を高めたいという場合は、私たちのYouTubeチャンネル(登録者数2200人突破!)をご活用ください。
「痩せる 運動」や「食後 運動」のヒント、
科学的根拠に基づく「タバタトレーニング」(私たちは開発者の田畑泉教授をお招きしてセミナーを開催した実績があります)など、
有益な情報を無料で得られます。
社内報などで共有するだけでも、立派な第一歩です。
第一歩を踏み出した企業の、その先の未来
この「小さな第一歩」は、やがて組織全体を動かす大きなうねりへと変わっていきます。
スモールスタートで手応えを感じた企業様は、次に「健康経営コンサルティング」へとステップアップしていきます。
単発のプログラム(点)が、年間の戦略的な計画(線)となり、組織全体を巻き込む文化(面)へと発展していくのです。
このプロセスでは、私たち健康経営アドバイザーが司令塔となり、
必要に応じて各専門家と連携しつつ貴社の経営課題に向き合います。
運動、食事、メンタルヘルスなど、
多角的な視点からのオーダーメイド支援を通じて、
貴社の健康経営を、一過性のプロジェクトから持続可能な成長エンジンへと進化させていきます。
健康経営が定着した企業の変化
健康経営が定着した企業では、目に見える変化が起こります。
まず、社員一人ひとりが心身ともに健康で、最高のパフォーマンスを発揮する、活力に満ちた職場が実現します。
朝のあいさつに元気があり、会議での発言も積極的になります。
次に、エンゲージメントが高く、
優秀な人材が「ここで働き続けたい」と心から思える、選ばれる企業になります。
離職率の低下と、求人への応募者数の増加という形で、数値にも現れてきます。
そして、Well-beingな社会の実現に貢献し、社会から信頼される、持続可能な企業へと成長します。
地域社会での評価も高まり、ビジネスパートナーからの信頼も厚くなります。
実際の成功事例として、ある企業では健康経営導入後3年間で離職率が30%減少し、
生産性指標が15%向上しました。
また、従業員満足度調査では「会社を友人に勧めたい」という項目で大幅な改善が見られました。
継続的な改善サイクル
健康経営は一度実施すれば終わりではありません。
定期的な効果測定と改善を繰り返すPDCAサイクルが重要です。
Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のサイクルを回すことで、より効果的な施策へと進化させていきます。
私たちヒューマンフィットネス東浦では、このサイクルを支援するため、
定期的なフォローアップと改善提案を行っています。
データに基づいた客観的な評価により、常に最適な健康経営戦略をご提案いたします。
まとめ:さあ、未来への第一歩を。あなたの「お問い合わせ」が会社を変える
本記事では、多くの企業が抱えるリアルな悩みから、
健康経営を始めるための具体的な第一歩までを、実際のお問い合わせ事例を基に解説してきました。
健康経営の成功に、魔法の杖はありません。
しかし、成功への確実な道筋は存在します。その道筋の入り口は、いつだって同じです。
それは、「専門家に相談してみる」という、とてもシンプルで、しかし勇気のいる一歩です。
この記事を読んで、少しでも心が動いた経営者様、健康経営担当者様。
漠然とした不安を、具体的な希望に変える旅を、ぜひ私たちと一緒に始めませんか?
貴社からの「お問い合わせ」という第一歩が、
会社を、社員を、そして未来を大きく変えるきっかけになることを、私たちは確信しています。
私たちヒューマンフィットネス東浦の取り組み
私たちヒューマンフィットネス東浦は、
単なるフィットネス指導にとどまらず、地域社会全体の健康向上に取り組んでいます。
東浦のマラソン大会を復活させる「第1回東浦健康ラン・ウォーク」の企画・運営や、ボランティア募集などを通じて、地域社会の健康にも貢献しています。
このような地域に根ざした活動を通じて培った経験と実績を活かし、
企業の健康経営においても、単なる表面的な施策ではなく、本質的で持続可能な取り組みをご提案しています。
健康経営は、企業の社会的責任を果たすという意味でも重要です。
従業員の健康を大切にする企業は、地域社会からの信頼も厚く、長期的な企業価値の向上につながります。
あなたの会社の未来は、今日のあなたの行動にかかっています。
まずは小さな一歩から、一緒に歩み始めませんか。
【健康経営に関するご相談・お問い合わせ】 どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ こちらをクリック
TEL: 090-4264-6609 ヒューマンフィットネス東浦
私たちは、貴社の健康経営成功を全力でサポートいたします。